修行時代に先生に言われた印象的な言葉【7】 ― 2012年08月09日 09時43分

「否定する事から文化が生まれる」
(クラウス・ヘルヴィッヒ先生)
日常会話の中で、相手の発言を遮って反論する。
すると相手はさらに違う角度から意見を述べて切り返し、
議論がだんだんと白熱していく。
こんな光景は、テレビの討論番組では良く見られる光景ですが、
普段、仕事の現場や仲間内でいちいち相手の言う事につっかかって
いたら、商談は進みませんし、そもそも会話に和やかな雰囲気
というものが無くなり、やがては社会的に不利益な立場に陥っていく
事でしょう。
しかし、こう考えるのは「いかにも日本人的な感覚だ」と
ヘルヴィッヒ先生は指摘します。
ベートーヴェンの作品110のソナタのレッスンを受けている時に
先生はこうおっしゃいました。
「第1楽章と2楽章のキャラクターをこれほど変えたのは何故だと思う?
それは全く違うものをぶつける事によって、新しい力を生み出す為だよ。
貴方(先生はいつも敬語です)の2楽章には、1楽章を否定するだけ
反抗精神が足りず、私には日本的(つまり過分に社交的)に聴こえます。」
天国的な世界を1楽章で描写した後、2楽章で怒りにも似たエネルギーを
もって「前言」を根こそぎ撤回・否定してこそ、絶望的なアリオーゾが生かされ、
ひいてはフーガという、より確信に満ちた答えと、爆発的な喜びに満ちた
フィナーレが 導き出されるのだと先生は説明して下さいました。
確かに、あの有名な「第九」も、主題の循環形式を取りつつも終楽章
において先の3つの楽章のテーマを、ご丁寧に歌詞(“その音ではない!”)
まで付けて全否定した結果、歓喜の歌のテーマが生まれるという形を
取っています。
つまり第九とは、提示しておいた古い考えを訂正してこそ、喜びの
エネルギーがより強力なものになる、という考えに基づいて構成
された曲なのです。
長いドイツ生活において、コミュニケーションを否定から生み出す、
という気質に私は 100%順応する事はできませんでしたが
(完全帰国の理由は、私は自分が典型的な日本人だと悟ったから
だと考えています)、ベートーヴェンの音楽やドイツという国を想う時、
いつも先生の言葉を思い出します。
音楽的なご指摘ではなく、文化の違いについてまで考えさせて
下さった先生に感謝しながら、次回ベートーヴェンを音にする時には、
私のDNAに欠落している 「強力な反骨精神」を呼び覚まして取りかかる
事にしましょう。
----------------------------
一週間、硬めな文章にお付き合いいただき有り難うございました!
仙台で皆様にお目にかかれるのを楽しみにしています。
青柳 晋(ピアノ)
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://sencla2012.asablo.jp/blog/2012/08/09/6536377/tb
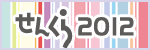

コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。